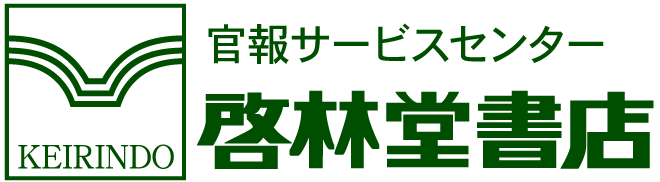10月号 2020.10.1
啓林堂書店 https://books-keirindo.co.jp/
私たちの日常には番号が溢れている。電話番号、郵便番号、車のナンバープレート、お好きな方であれば野球選手の背番号、というのも浮かぶかもしれない。最近であればマイナンバーなど、身近な例を見渡してみても枚挙にいとまがない。我々の生活はそれほどまでに番号と密接に関わっている。
一元管理をするために振られたこれらの番号は、一見無味乾燥なイメージで受け止められがちだ。だが本書『番号は謎』(新潮新書)は、その番号が誕生した経緯、運用のされ方などを読み解いていくことで、背後にある意外なドラマを教えてくれる。
例えば電話番号。昔は東京と大阪では桁数が9桁、その他の市は10桁の番号だった。そのため昔は番号が多いと田舎者だと揶揄する向きもあったようだ。だが時代を下るにつれて使用される電話番号が増えて行き、空き番号の残りが少なくなってきた。全ての番号が10桁となるも追いつかず、この問題を解決すべく取られたのが、市外局番の末尾を市内局番の頭に押しやるという面白い方法であった。番号自体は変わらないが、市外局番の末尾番号が一つ減り、代わりに市内局番の頭番号が一つ増える。それだけで使える番号が増えるとは…? これは電話番号のとある法則による。
また、市外局番はひとつ、または複数の自治体のに集まりに対応していることが多いのだが、はみだし市外局番も存在している。これは電話回線が我々の生活に根差しているがために起きた違いなのだが…思わず地図を引っ張り出してきて確認してしまった。納得の答えは本書にて。
また、今ではすっかりおなじみの郵便番号。これは郵便システムの合理化を推し進めるために旧郵政省が注力したものである。当時深刻になりつつあった郵便物仕分けの人手不足を解消すべく、郵便物の振り分けを機械で自動で行えるように動いたのがそもそもの始まりだ。封筒やはがきの上部には現在郵便番号を書き込む赤いマス目が並んでいるのが主流だが、これはその時の働きかけから登場している。
郵便番号が面白いのはそのナンバリングの法則だろう。頭の00が札幌市から始まり、通常ならそのまま北から順に南下してきそうなものなのだが、郵便番号の場合は01秋田、02岩手、03青森とつづいたあと、04から09は北海道に戻り、10番台はなぜかいきなり東京に飛ぶ。当時の郵便事情を反映した面白い理由が述べられているので、ぜひ注目してみて欲しい。
さらに鉄道からは駅のホーム番号が紹介されている。○番線、とされる番号の振り方は駅長室に近い方から1番線、2番線…と始めるのが一般的なようだが、規則で決まっているというわけではないらしい。なお、0番線があるのに1番線がない!? といった不思議な駅も紹介されている。欠番が生じる理由とは? なおハリー・ポッターに登場するキングス・クロス駅は、ハリーたちが魔法学校へと向かう9と3/4番線のホームで知られているが、観光客向けの案内板はあるものの架空のホームなので残念ながら実在はしない。
法則通りであれば分かりやすいところ、様々な配慮がなされた結果、複雑怪奇な様相を見せる番号たちが数多く紹介されている。番号についてここまで体系的にまとめた本は珍しい。本書を読み終える頃には、すっかり番号の虜となっていることだろう。
【ナツメ社】かみゆ歴史編集部/編著
学生の時に出会っていれば、歴史の理解がもっと深まったのではないか…? と、少しくやしくなってしまった一冊。変わった横長の判型は紙面をビジュアル重視で構成しているため。豊富なイラストと分かりやすい解説によって、日本史の全体的な流れを無理なく自然につかむことができるよう工夫されている。
本書を読むと、歴史は切り離されたひとつひとつの事柄ではなく、積み重なっている事象の連続であるというのがよくわかる。学生の方はもちろん、教養として日本史の学びなおしを考えている社会人の方にもおすすめ!
≪今月の担当≫ 商品部 部長 佐藤篤志
ダーウィンの進化論が熱い、自分の中でだが。進化論曰く「自然選択によって、生物は環境に適応するように変化し、分岐して多様な種が生じる」という。これについては賛否あり、進化論では説明がつかない生き物もいる。それは人である。なぜならサルから人に進化した中間の生き物が見つかっていないのだ。いわゆるミッシングリンクだ。まあ、たまたま見つかっていないだけかもしれないが、もしかしたら・・・。ふと昔読んだSF小説、J・P・ホーガンの「星を継ぐもの」で面白い結論を出していたことを思い出した。秋の夜長に読んでみるのもよいかもしれない。
新聞の書評欄を良く読みます。何か面白い本はないかと楽しみにしているのですが、ごくまれに偶然メルマガで紹介しようと思っていた本を先に見つけてしまうことも。しまった、先を越された! とも思うのですが、面白い本だったしなと、納得することの方が多いです。
◆外商部おすすめの児童書・奈良本のご紹介◆
啓林堂書店ホームページ・外商部ページ( https://books-keirindo.co.jp/gaisyoubu/ )にて、
更新中の「外商部おすすめの奈良本」「おすすめ児童書」をご紹介!
おすすめ児童書
『とんとんとめてくださいな』
【福音館書店】こいでたん/文 こいでやすこ/絵
森の中で道に迷った3びきのねずみ。小屋のドアをたたきます。「とんとんとめてくださいな」
返事がなく、小屋の中にはだれもいません。
2ひきのうさぎや3びきのたぬきもやってきて、一緒にとまらせてもらうことにしました。
すると、この小屋の主人が帰ってきました。だれなんでしょう。ちょっとドキドキしちゃうお話です。
古代に都がおかれ、東アジア諸国の文化・情報を受容する拠点であった奈良。日本最古の寺院の飛鳥寺、百済大寺と呼ばれた吉備池廃寺、新羅の感恩寺を模した本薬師寺…。飛鳥・白鳳時代の二五寺院などを、発掘成果と『日本書紀』などを検証し、平易に紹介。古代の有力氏族が建立した寺院跡の所在地と瓦類から有力氏族相互の政治・経済関係に言及する。
お問い合わせ窓口
問い合わせフォーム https://books-keirindo.co.jp/contact/
本のご予約・ご注文承ります。ご意見・感想・ご要望などお待ちしております。
発 行 (株)啓林堂書店
〒639-1007 大和郡山市南郡山町527-13 TEL/0743-51-1000
文 責 (株)啓林堂書店
〔外商部〕 上田輝美
啓林堂書店 ホームページ
https://books-keirindo.co.jp
※本メールの無断転載を禁じます。
Copyright (C) 2020 Keirindo Shoten. All Rights Reserved.