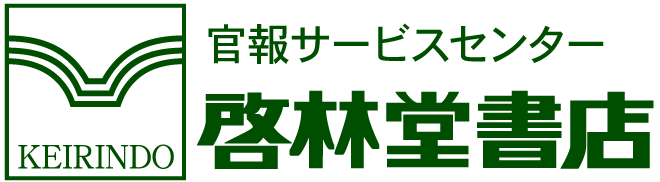2月号 2021.2.1
啓林堂書店 https://books-keirindo.co.jp/
連日取り上げられる新型コロナ関連のニュースにより、生活の中の衛生について考える機会が多くなっている。そんな衛生全般について、分かりやすくまとめられた児童書が刊行された。
『こども衛生学』(新星出版社)、本書によると、「衛生」とは、いのちや生活をまもるという意味なのだそう。
本書では感染症予防の考え方や、食べ物の安全など、子どもにも身近な話題を中心に、衛生学の基本が学べる内容となっている。
「衛生」のはじまりは、都市が発達し、貿易などで人の往来がさかんになったときに発生したコレラなどの伝染病の流行防止からだ。汚い水や大便・小便の処理など、生活環境を清潔にする運動から健康を守る取り組みが始まった。環境浄化運動から始まった衛生の取り組みは、その後「衛生学」としてまとめられることになる。
なお、「衛生」という考え方自体は約4000年前からあったと言われている。古代エジプトの遺跡から、浴室や排水管、排水溝が発見されており、紀元前2100年頃には手を洗う習慣があり、人々が衛生面に注意を払っていたのが分かっているのだそうだ。日本においても、まだ「衛生学」の考えが確立していなかった江戸時代、江戸などの都市部でコレラなどの伝染病対策に取り組んでいる。主に飲料水を確保するための上水道の設備、清潔を保つための公衆トイレの設置、また、井戸を共同で管理するなどしていたという。
昔から人々は健康を脅かす問題や原因と常に向き合ってきた。第1章以降は、現代に生きる私たちの暮らしに関わる衛生学について、理解を深めていくことになる。
コロナが猛威を振るう中にあって、最近はどこへ出かけるにもウエットティッシュがないと落ち着かない、そんな方も多いのではないだろうか。だが、表記でよく見かける「抗菌」「除菌」「殺菌」、実はそれぞれ少しずつ意味が異なっている。
本書、「おしぼりで手をふけば、菌はなくなる?」の項目をご覧頂きたい。31ページに、「菌をなくすレベル」順に、わかりやすくまとめられた表が掲載されている。実は菌を完全に殺すのは「滅菌」と書いてあるものだけ。当然おしぼりで手をふいたくらいでは、菌は減らすことはできても、完全になくすことはできない。だが菌がなくなればいいかというとそうではない。薬品が強くなるとその分、物や肌への刺激も強くなってしまう。私たちは望む効果を確認した上で、これらを適切に使い分ける必要があるのである。
また、初歩的だがとても大事な「手あらい・うがいはなぜするの?」という項目。手洗い・うがいには、病原体が体に入るのを防ぐ効果がある。
手洗いの効果はすさまじく、水で15秒洗うだけでも、ウイルスの数を約100分の1まで減少させることができる。ハンドソープを使って手を洗うと、ここからさらに100分の1、ウイルスの数を減少させることになるのだそうだ。正しい手洗いをすることで、手に付着しているウイルスの数はぐっと減る。本書では念入りに洗った場合のそれぞれの調査結果もまとめられているので、ぜひご確認いただきたい。
小中学生向けにまとめられた児童書のため、分かりやすく優しい表現でまとめられているが、網羅している範囲が広く、大人が読んでも勉強になる。今更聞けない基本もこの一冊がきっと解決! まずは気になった項目から、読み進めてみては?
【平凡社新書】 八木正自/著
本書で主に取り上げられる古典籍とは、明治時代以前の本のうち、文学的価値、歴史的価値があるとされる本のことである。価格にすると数万、高いものであれば数千万円と金額を聞いただけでも目がくらむ。「古本」「古書」とはどう異なるのかについても冒頭で触れられているので、確認してみて欲しい。
著者が古典籍の世界へ足を踏み入れたきっかけ、過去に外国人が日本から持ち出した絵画、浮世絵版画、歴史資料などの貴重史料を著者が海外から逆輸入した話、また東京で開催される古書業者市でのオークションの様子など、普段あまりなじみのない古典籍の世界をひもとく興味深い一冊となっている。
国宝級のお宝とどのようにして著者が出会ってきたのか。必見!
≪今月の担当≫ ジュンク堂書店奈良店 店長 中村潔
実家に暮らしている時は積読でも良かったが、結婚して本の置き場所が難しくなってきた。
仕方なく電子書籍も購入するようになったのだが、読み物はともかくビジネス書などの図表が中に入る本だと途端に読みづらくなる。段組みが上手く出来ないために、拡大縮小をしながら読む事になりなかなか頭に入らない。料理の本も同じようにスマホだと読みづらいらしく、電子と本の使い分けは大きな問題である。ただそれ以上に実家の本をどうするかに頭を悩ませている。
先月号のメルマガで紹介した『お探し物は図書室まで』が本屋大賞にノミネートされました! まだ読んでいないという方、ぜひ読んでみてください。司書の小町さんが好きになってしまいますよ!
◆外商部おすすめの児童書・奈良本のご紹介◆
啓林堂書店ホームページ・外商部ページ(https://books-keirindo.co.jp/gaisyoubu/)にて
更新中の「外商部おすすめの奈良本」「おすすめ児童書」をご紹介!
おすすめ児童書」「おすすめの奈良本」3月号は、2月下旬に更新予定です!お見逃しなく!
ある日、ととさんは腹が痛くなって、和尚さまの言う通り、かえるをのんだ。
腹は治るが今度はかえるが気持ち悪い。次はかえるを退治するためにへびをのむ。
その次はへびを退治するためにきじをのむ。最後には鬼までのんで、さあ鬼はどうやって退治しようか。
節分の豆をまいて鬼退治。めでたしめでたし。
わが国最初の官立寺院である大安寺の宗教的意義や文化的意義を、様々な研究成果により再認識する講座「大安寺歴史講座」第四弾。
「大安寺伽藍縁起并流記資財帳」を丹念に読み込み、奈良時代の大安寺が行った宗教・経済活動の実体を探究。安置仏像の全貌と歴史的背景、それを踏まえた道慈の事績解明、20点余りの図版による食堂など境内の周辺施設の復原は、大安寺研究に新たな問題を提起する。
お問い合わせ窓口
問い合わせフォーム https://books-keirindo.co.jp/contact/
本のご予約・ご注文承ります。ご意見・感想・ご要望などお待ちしております。
発 行 (株)啓林堂書店
〒639-1007 大和郡山市南郡山町527-13 TEL/0743-51-1000
文 責 (株)啓林堂書店
〔外商部〕 上田輝美
啓林堂書店 ホームページ
https://books-keirindo.co.jp
※本メールの無断転載を禁じます。
Copyright (C) 2019 Keirindo Shoten. All Rights Reserved.