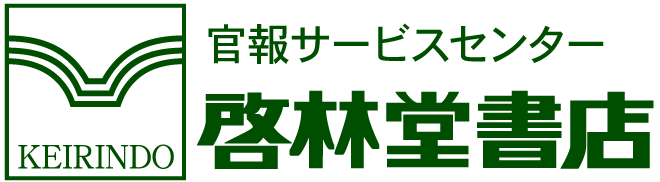6月号 2019.6.3
啓林堂書店 https://books-keirindo.co.jp/
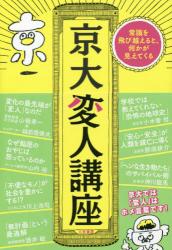
「京大変人講座」とは、京都大学発の、京大に連綿と受けつがれている「自由の学風」「変人のDNA」を世に広く知ってもらうため発足した公開講座のことだ。(京大で変人はホメ言葉である。)本書はその人気の授業を書籍化したものである。(三笠書房刊)
サービス経営学、法哲学、システム工学など、様々な分野の先生の話はどれも一風変わっていて面白い。
特に面白いと感じた話を次より少し紹介してみたいと思うが、関西気質を感じられる序章のダイアローグとディベートの違いの話などもかなり楽しい内容となっているので、読み飛ばさず、ぜひ冒頭から読んでいってみて欲しい。 まず、第1章の『毒ガスに満ちた「奇妙な惑星」へようこそ』。章タイトルに思わずびっくりしてしまうが、これは地球のことである。
私達が生きていく上で酸素の存在は必要不可欠。だが、原始の生物に取って酸素は毒だった。なぜ私達は酸素を必要とする生物になったのだろう? これは“変な生き物”だけが生き残った結果だというが・・・。他にも誰も見たことがないはずの地球の内部構造がなぜ解明されているのか、黒い地層が教えてくれる海の超酸欠事件など、興味深い話が多数登場する。恐竜は隕石によって絶滅した言われるが、それよりも昔、海の生物に絶対的な危機が訪れていた。海の中の酸素が極端に少なくなったのである。それは黒い地層から分析できることなのだが・・・地層が黒くなっている理由に驚いた。もう一つ、第4章の『なぜ、遠足のおやつは“300円以内”なのか』。
便利なことが推奨され、喜ばれる世の中である。不便よりも便利な方がいいと多くの人は考えているだろう。だが、本当にそうだろうか?
本章で紹介されているクラシエの「甘栗むいちゃいました」と「ねるねるねるね」はどちらもおなじみのヒット商品だが、かたや甘栗の皮がすでに剥かれている便利な商品、もう一方は粉末に水を加えて練るという、手間を加えて作るおやつという対照的な商品である。便利なだけが商品の価値になっていないのが分かるが、一体何故「ねるねるねるね」は売れているのか、分かるだろうか?
また、章のタイトルにもある遠足の話。決められた値段内で何のおやつを買うか友達と悩んだという人は多いと思う。ではもし、おやつを買える金額に制約がなかったとしたら・・・? 遠足はより楽しいものになっただろうか、それとも・・・
さらにもう一つパイロットの例。難しい試験に合格し、念願かなって現場にパイロットとして配属。しかし機体にはすでに自動運転の機能が備わっており、パイロットは何もしなくてよいという。この時パイロットはどう思うだろう。一概に何もしなくて楽だと思うのだろうか?
実は便利になったことで失われたものがある。一見不要の制約やあえての不便さから生まれるものに目を向けてみると、そこには「発見」があった。
「常識」だと思っていることを少し違う視点から見てみると、面白いことに気づけるかもしれない。
個性的な先生たちの話はどれも興味深い。早くも続編刊行が決まったようだ。発売を楽しみに待ちたい。
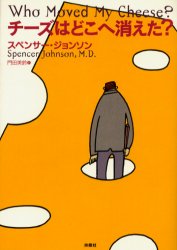
【扶桑社】スペンサー・ジョンソン/著、門田美鈴/訳 ¥905
ベストセラーにもなった平成で最も売れたビジネス書をもう一度。今年の2月には続編も刊行された。
「迷路」の中に住む2匹のネズミと2人の小人。
彼らは「迷路」のどこかにあるという「チーズ」を探している。この作中に登場する「チーズ」はただの食べものではなく、私達が人生で追い求めるもののシンボルだ。苦労しつつもネズミと小人はそれぞれの方法で、「チーズ」を見つけることに成功する。だが、苦労して見つけた「チーズ」はある日忽然と姿を消してしまった。その時、彼らは・・・?
変化してゆく状況にどう対応すればいいのか? シンプルな話の中に問いと気づきがある。もしも似たような状況に陥ったら、この話を思い出してみよう。
さぁ、勇気を出して、新しいチーズを探しに行こう!
≪今月の担当≫ 外商部 上田輝美
本を読み出すと何も聞こえなくなると昔からよく言われた。物語の中にどっぷりとはまり込んで抜け出せなくなるのである。ただ、小さい頃とは少し読み方が変わったようで、絵本や児童書であっても必ずしも主人公の視点では読まなくなくなった。
感情移入を全くしない訳ではないが、どちらかというと第三者視点で天井や壁に張り付いて物語の主人公をじーっと観察している。たまに野暮なツッコミを入れたくなるため、しゃべらない無機物の方が自分には都合がよい。(通行人では声が出てしまう。)神の視点にはなれそうもない。勝手な予想をしたり妄想したりと好き勝手に横道に逸れすぎる。やはり第三者視点が一番しっくりくる。
正当な文学路線の読み方とは程遠いのだろうなと思いつつ、自分なりに今も楽しく読書を楽しんでいる。
特典でもらうブックカバー。もらうのは嬉しいのですが、どう収納するかでいつも頭を悩ませています。
きれいな状態で保存しておくか? はたまたお気に入りの本にかけてみるか。カバーする時は最初に折り目をつけるところで、いつも二の足を踏んでいます。
◆外商部おすすめの児童書・奈良本のご紹介◆
おすすめ児童書
『あめふりさんぽ』【講談社】江頭路子/作
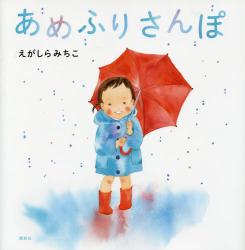
外は雨。お気に入りのかさ、長靴、カッパで女の子は散歩に出かけます。
途中で出会った かたつむり、あじさい、おたまじゃくしが困っている様子をみた女の子は…。
やがて雨は止んでお日様が顔を出すと空には虹!
リズミカルなことばも楽しい雨の日の絵本。
おすすめ奈良本
『橘諸兄』 【吉川弘文館】 中村順昭/著 6月21日発売予定
奈良時代の政治家。母の橘三千代の死後、臣籍降下して橘諸兄(もろえ)となる。藤原四兄弟が疫病に倒れると政権の中枢に立ち、聖武天皇の度重なる遷都や東大寺大仏の造営など、天平期の諸政策を主導するが、藤原仲麻呂の台頭で失脚する。五世王にすぎなかった諸兄はいかにして政界の頂点に登りつめたのか。最新の発掘成果にも触れつつその生涯を描き出す。
お問い合わせ窓口
問い合わせフォーム https://books-keirindo.co.jp/contact/
本のご予約・ご注文承ります。ご意見・感想・ご要望などお待ちしております。
発 行 (株)啓林堂書店
〒639-1007 大和郡山市南郡山町527-13 TEL/0743-51-1000
文 責 (株)啓林堂書店
〔外商部〕 上田輝美
啓林堂書店 ホームページ
https://books-keirindo.co.jp
※本メールの無断転載を禁じます。
Copyright (C) 2019 Keirindo Books Co.,Ltd. All Rights Reserved.