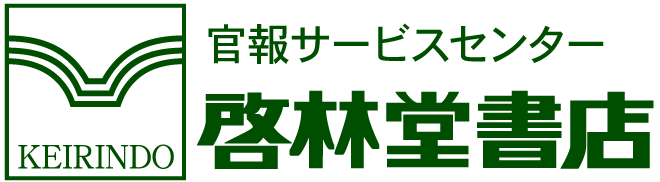8月号 2022.8.1
啓林堂書店 https://books-keirindo.co.jp/8
“不可抗力だらけの駅員の日常を覗くことで、小さな悩みが吹き飛ぶ、すべての現代人必読の社会派エッセイ”。
帯でそう紹介される本書タイトルは、『怒鳴られ駅員のメンタル非常ボタン 小さな事件は通常運転です』(KADOKAWA)。タイトルがすでに駅員の苦労を物語っているが、決して駅員の苦労話だけを扱っているわけではない。知っているようで知らない駅の裏側は利用者からは見えていない駅の違う側面を知れて面白い。また、著者が日々過ごす中で見つけた小さな気づきや働く上での考え方、心得などは鉄道にあまり興味のない私にもなるほど、と思えるような、日々の生活のヒントを示してくれている。
著者が最初に配属された駅は一日10万人が利用する駅。通勤客で混み合う改札、駅員はポツンとひとり。これだけでめまいがする心地だが、インパクトの強かった話をいくつか紹介してみる。
「苦情が電車に乗ってくる」。パンチの効いたサブタイトルだ。今すぐにでも逃げ出したい。
乗客に声をかけられた著者。駅案内かと話を聞いてみると、離れた駅のクレームだったそう。なぜ他の駅で感じた不愉快をここで? この時は事実関係確認の上で、再度お詫びの連絡を該当駅からする段取りになったようだ。
著者は言う。同じようにこの駅での苦情が、他の駅に寄せられているかもしれない。苦情が大事にならないよう、うまく話をまとめてくれているかもしれない・・・駅はチームプレーで、鉄道会社全体を見渡す必要がある。著者の冷静な視点に好感が持てる。
急いでいるんだけど、と客に急かされる。たまに見かける光景だ。この時は特急券の発行に焦った結果、普段しないようなミスをしてしまいやり直しになったそう。余計に時間がかかる。当然客は怒る。悪循環だ。
著者は、先輩から急いでいるお客様に対しては逆にゆっくりと対応するよう言われていたことを思いだす。ゆっくり、というのは普段やっている作業を確実にこなす、ということ。やり直したせいでかえって時間がかかってしまっては本末転倒。普段の自分を顧みて、気を付けなくては、と姿勢を正した。
かなり厄介だな、と感じたのはICカード絡みのトラブルだ。利用者には便利なのだが、対応する駅員にはかなりネックになっているように感じた。タッチ一秒順守は些細なトラブルを未然に防ぐ。特にスマホに搭載したICカード機能に関わるトラブルは読んでいるだけで疲れてしまった。なんでも機能を一つにまとめれば便利なのだろうか? リスク分散、あえて分けるという考えも大事なように思う。
ひとまず、スマホでなんでも済ませようという人はバッテリーは自分のためにも常備しておくのが安全だろう。
第4章の修羅場十選は特に読んでいてハラハラした。こんな場面には居合わせたくないと思うものばかりであるが、どうやってその場面を著者が切り抜けてきたのか、ぜひ本書で確認してみて欲しい。
駅員の視点が良くわかる良質エッセー。駅員の視点を知ると、マナーの良い利用者でありたいなと強く思う。おすすめ!
大ヒットシリーズより、四半世紀の研究をまとめた新シリーズが登場。マンガやアニメに登場する場面をまじめに解明していくと、意外にも残念な現実が明らかに・・・。
ドラえもん、鋼の錬金術師、刃牙、鬼滅の刃など、新旧問わず有名な作品が幅広く題材として取り上げられている。
地球を守ってくれているウルトラマンや仮面ライダー。だが、お決まりのように偽物が登場したとき、本物と偽物の区別がつかないのはなぜなのか? 人間の視点で見てみると、意外な盲点があったことに気づく。
今からシリーズをそろえたい! という方には特にオススメ。昔シリーズをそろえていた、という方も情報がアップデートされている箇所があるので一読してみてはどうだろう?
≪今月の担当≫ 学園前店 社員 中西哲夫
先日ふと思い立って、大規模な部屋の模様替えを行った。
長年使っていた本棚やラックが、大きい割にいまひとつ使い勝手が良くないことや、もともと広くない部屋にベッドと、趣味で買い集めたCDやレコード、本などが棚に入りきらないくらいあって、さらに狭くなっていた状況を改善したくなったのだ。
数日かけて棚やベッドを撤去し、そこに新たに購入した本棚を置いた。そして、雑然と積み上げられていた本や雑誌を、そこに並べていく。今まで狭く感じていた部屋に、同じ空間とは思えないほどの開放感が生まれた。
大きめの本棚を購入したおかげでまだ収納に余裕があり、いまは、そこにどんな本を買って並べようかと考えている。
モノをため込む性格は、一向に治る気配がない。
夏休み。小学生くらいの子が児童書コーナーではりついている姿をよく見かけるようになりました。親御さんに嬉しそうに選んだ本を持っていく様子がとても微笑ましく思います。
◆外商部おすすめの児童書・奈良本のご紹介◆
啓林堂書店ホームページ・外商部ページ( https://books-keirindo.co.jp/gaisyoubu/ )にて、
更新中の「外商部おすすめの奈良本」「おすすめ児童書」をご紹介!
昆虫の体重って何グラムか知っていますか。
手のひらにのせても重さを感じないほどの小さい昆虫の体重は、普通のはかりでははかれないのです。
ではどうやってはかるのでしょう。そして、何グラムなんでしょう。
1円玉と比較したり、オスとメスや幼虫と成虫の体重の違いも教えてくれます。
外商部おすすめの奈良本
『東アジアからみた「大化改新」』
【吉川弘文館】
仁藤敦史/著
8月18日発売予定
「大化改新」は東アジア世界にどう位置づけられるのか。高句麗・百済・新羅の動向や外交政策の対立などから、新たな視点で再検討。
お問い合わせ窓口
問い合わせフォーム https://books-keirindo.co.jp/contact/
本のご予約・ご注文承ります。ご意見・感想・ご要望などお待ちしております。
発 行 (株)啓林堂書店
〒639-1007 大和郡山市南郡山町527-13 TEL/0743-51-1000
文 責 (株)啓林堂書店
〔外商部〕 上田輝美
啓林堂書店 ホームページ
https://books-keirindo.co.jp
※本メールの無断転載を禁じます。
Copyright (C) 2020 Keirindo Shoten. All Rights Reserved.