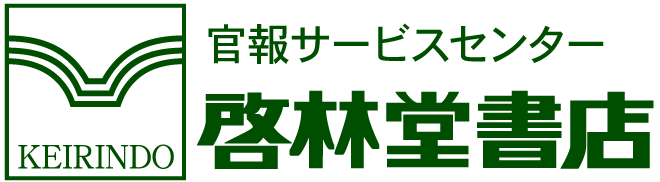9月号 2020.9.1
啓林堂書店 https://books-keirindo.co.jp/
今回ご紹介するのは『考えるナメクジ 人間をしのぐ驚異の脳機能』(さくら舎)。うわ、ナメクジ!? と思われた方、回れ右をするのは少し待って欲しい。
ナメクジといえば農作物の害虫で有名である。英語ではのろまの代名詞として使われるなど、やはりそのイメージは良くない。雨の降った後、鉢植えをどかすとよく遭遇するが、その見た目や、ナメクジが這って移動した跡がべたべたしているのが嫌だ、という方も多いのではないだろうか。
だがそんな嫌われ者のナメクジ、実は賢く、学習能力もある。特筆すべきはその脅威の回復力である。
ナメクジはカタツムリやクリオネと同じ巻貝の仲間ではあるが、別の種である。ナメクジはカタツムリと違って背中に殻を持っていない。なお、カタツムリは殻の中に大事な内臓をしまいこんでいるため殻を脱ぐことはできない。見た目は少し似ているが、全く別の生き物なのである。
また、ナメクジといえば塩をかければ溶けると認識している方も多いと思うが、実際には溶けている訳ではない。体のほとんどが水分でできているために浸透圧によって多量の粘液と水分を放出して縮んでしまう様子が溶けているように見えるのである。
なお、発達してるのは触覚。視覚、触覚、嗅覚を感知している大触角で、彼らは安全な場所や食べられそうな餌を探す。
また、ナメクジにはより暗い場所を好む性質(負の光走性)がある。頭から生えた二本の触角センサーを比較して、より暗い方に行きたがるのだ。これを利用した面白い実験が紹介されていた。
まず好物である野菜ジュースを暗い場所に置いてナメクジを誘導するのだが、ナメクジが食べようとしたタイミングでキニジン硫酸水溶液(嫌なにおいがするもの)をかけ、ジュースのにおいを嫌いにさせる。するとその後はジュースが暗い場所に置かれていても近寄ろうとせず、ナメクジは明るい場所に戻ろうとするのだそう。しかし本能的に明るい場所も嫌いなナメクジは、暗い側に進むことも明るい側に進むこともできなくなってしまう。同じ場所を行ったり来たりして葛藤、苦悩している様子が見て取れるそうだ。
ではそんなナメクジの大事な触角や脳が重大なダメージを受けた場合、一体どうなってしまうのだろうか? 当然生きては行けないと考えてしまうのだが、ナメクジの再生能力は予想をはるかに超えてすさまじかった。つぶれてしまった前脳葉は一ヶ月、切断された触角も数週間程度で回復してしまう。人間にはおよそできない芸当である。なお、ナメクジの触角にはさらに面白い役割がある。先程紹介したセンサーとしての役割だけでなく、実は脳のような働きも行っているのだが・・・この詳細は、ぜひ本書でお確かめ頂きたい。
ナメクジの生態もさることながら、マイナー生物ならではの思いがけない著者の苦労話なども面白いのでこちらも要注目。
身近であるものの、嫌悪感が先に立ってその生態をよく知らなかったのだなと痛感した。興味がわいてきたのであれば、ぜひ本書を読んでみて欲しい。これまでのナメクジの印象がガラリと変わるはず。
【ワニブックス】 キムスヒョン/著 吉川南/訳
韓国で80万部、日本でも35万部を突破の元気をもらえるイラストエッセイ!!
人と比べて生きるのはもうやめよう。世界にたった一人しかいない“自分”を大切にして生きていくために。
誰しもが抱く不安や、悩み、理不尽な憤りに寄り添い、時に深く切り込む。今を必死に生きようとしている“ごく普通”の人へと向けた著者の言葉は、きっと私たちを前向きにしてくれる。
≪今月の担当≫ 外商部 部長 森川永夫
<Web会議>
本屋でも会議はあります。毎月、各店舗の状況報告や今後の展開などを企画する店長会議に外商部も参加しております。が、新型コロナの影響でZOOMでの「Web会議」となり、リアル会議では声のボリュームや相槌のタイミング等、無意識にやり取りしていた事がオンラインでは相手のテンポを乱してしまう事となり戸惑いを感じています。
でもこんな時に救いを求めるのがネットの情報ではなく書籍にたよってしまう自分は本屋の人間なんだな~とふと思います。あっ、ただ歳のせいかも。
まだまだ暑い日が続いています。猛暑ピーク時、店頭に到着した本の箱を開けてみたところ、中からありえないような熱気が・・・! 本まで熱い。どうやら本と一緒に熱まで箱に運ばれてやってきたようです。
いつもより異様に熱くなった本を手に取りながら、今年の猛暑を実感していました。
◆外商部おすすめの児童書・奈良本のご紹介◆
啓林堂書店ホームページ・外商部ページ( https://books-keirindo.co.jp/gaisyoubu/ )にて、
更新中の「外商部おすすめの奈良本」「おすすめ児童書」をご紹介!
バナナくんは五人家族。ぼくはまだまだ青いんだ。
おじいちゃんおばあちゃんはすっかり熟して、チョコバナナやアイスバナナにへんしーん!
近所のおじいちゃんおばあちゃんもすてきにへんしんして、みんなでパーティーです。
どんなじいちゃんバナナになろうかな、バナナくんは楽しみでたまりません。
本書では、入江泰吉が撮影した写真と、万葉歌126首を掲載。郷愁誘う美しい奈良の風景とともに、万葉集の世界を堪能できます。文字だけでは読み解きにくい万葉歌ですが、写真と組み合わせることでより身近に感じることができます。それぞれの歌には現代語訳も掲載。英訳もあるので外国人の方にもおすすめです。読み進める順番に決まりはありません。好きな写真、好きな歌、どのページから開いてもかまいません。「万葉集って難しそう」と思っている方にこそ読んでほしい一冊です。
お問い合わせ窓口
問い合わせフォーム https://books-keirindo.co.jp/contact/
本のご予約・ご注文承ります。ご意見・感想・ご要望などお待ちしております。
発 行 (株)啓林堂書店
〒639-1007 大和郡山市南郡山町527-13 TEL/0743-51-1000
文 責 (株)啓林堂書店
〔外商部〕 上田輝美
啓林堂書店 ホームページ
https://books-keirindo.co.jp
※本メールの無断転載を禁じます。
Copyright (C) 2020 Keirindo Shoten. All Rights Reserved.